色々な音楽の起源を探ってきましたが、我々日本人にとっての最古の音楽はなんなのでしょうか。今回は「邦楽」について調べていきましょう。
今日では日本で作られたポピュラー音楽を外国の音楽「洋楽」と区別する為に「邦楽」と言っていますが、今回取り上げるのは狭義の意味の「邦楽」であり、いわゆる伝統的な日本の民族的、古典的な音楽の意味で考えて下さい。では、日本最古の音楽とは一体なんなのでしょうか?例によって確実な実態は分からないですが、縄文時代に土で作った笛や鈴があり、弥生次代には音階を出せる笛もありました。有名な「銅鐸」も実は楽器です。山梨の釈迦堂遺跡からも土笛が出土されています。
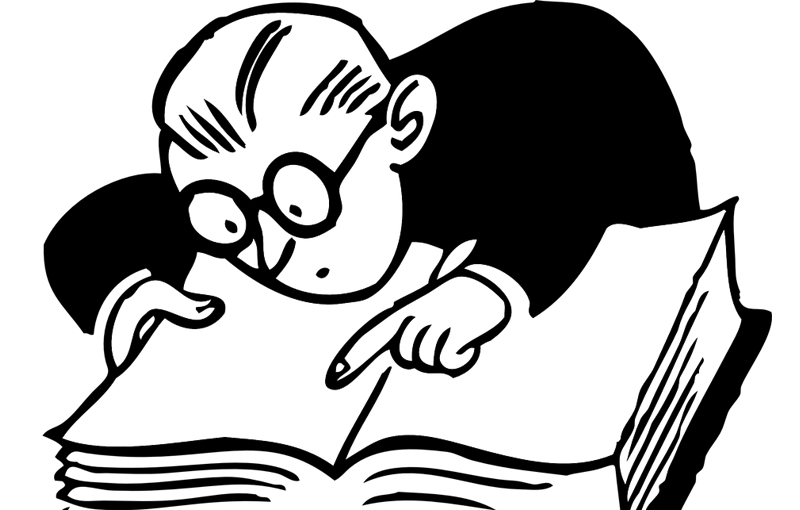
風土記や「万葉集」にも記述がありました。祭祀、農耕儀礼、民族行事など歌を唄う機会はいくらでもあったでしょう。その時代の楽器としては「コト」「フエ」「ツヅ」があったようです。
万葉集・管16‐3886の乞食者(ほかひびと)の詠に「笛吹きと 我召すらめや 琴弾きと 我召すらめや」という一文があります。乞食者(ほかひびと)とは芸能民の事で、歌や演奏、踊りなどもしたかもしれませんが、万葉集の編纂された七世紀頃にはもう笛や琴があり、演奏されていただろう事がうかがえます。

大宝元年(701年)に制定された大宝律令には、雅楽寮(うたまひのつかさ)と言う音楽専門の部署が設置されたようです。歌師、舞師、笛師、楽師などがいて、倭楽と雅楽を担当する部署がありました。雅楽は渡来人が担当していたそうです。雅楽って外国由来の音楽なんですね。また、笛師には笛工なる笛職人が付属したそうです。もうこの頃には日本で楽器が製造されていたのでしょう。
音楽に歴史あり、ですね。



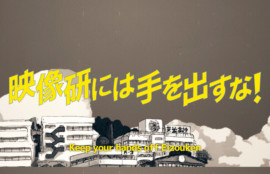











この記事へのコメントはありません。