私たちが日常的に使う「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」。
当たり前のように歌ったり、楽器で弾いたりしていますが、よく考えると不思議ですよね。
なぜ“ド”から始まるのか?
そして、なぜ英語だとCから始まるのか?
今日は、そんな身近だけど奥が深い音階の物語をのぞいてみましょう。
📜 起源はラテン語の賛美歌
「ド・レ・ミ」という呼び名は、11世紀ごろの中世ヨーロッパで生まれました。
修道士であり音楽理論家のグィード・ダレッツォが、当時の弟子たちに音階を覚えやすくするために、賛美歌の各節の冒頭の音節を利用したのです。
賛美歌「Ut queant laxis」から:
- Ut queant laxis(のちに「Do」に変化)
- Re sonare fibris
- Mi ra gestorum
- Fa muli tuorum
- Sol ve polluti
- La bii reatum
- Si → “Sancte Iohannes” の頭文字
こうして、現代でも使われる音階名の原型が生まれました。
🔄 なぜUtがDoになった?
「Ut」は発音しにくかったため、イタリアでより歌いやすい**「Do」に置き換えられました。
一説には、音楽理論家ジョヴァンニ・バッティスタ・ドニ(Doni)**の名前にちなむという説もあります。
また「シ(Si)」についても面白い逸話があります。
国によっては「Si」ではなく「Ti」と呼ぶ場合があり、これは発音の明瞭さや混同を避けるために改訂されたものです。
🌍 国ごとの音階の呼び方
音階は世界共通ではありません。
- 日本・イタリア・スペインなど:ド・レ・ミ方式(固定ド)
- 英語圏:C・D・E方式(移動ド/固定ドの併用)
- ドイツ語圏:H(シ)やB(変ロ)など独自表記
例えば、ドイツ語圏ではBとHを明確に区別するため、クラシック譜面にも「H」の文字がよく登場します。
バッハ(B-A-C-H)自身の名前も音に変換できるため、作曲に組み込まれたりします。
🎶 音階が文化を映す
「ド」から始まる音階は、ヨーロッパの宗教音楽とともに広まりました。
一方、ジャズやポップスの現場では、C・D・Eでの会話が主流です。
演奏の場やジャンルによって、同じ音でも呼び方が変わるのは、まさに文化の違いが音に宿る瞬間と言えるでしょう。
🗣 あなたはどの方式で覚えた?
ピアノや声楽で「ド・レ・ミ」を習った人もいれば、ギターで「C・D・E」から始めた人もいますよね。
どちらの方式でも、その背後には千年前の修道士たちの工夫と歴史が息づいています。
今度「ド」を口ずさむとき、少しだけ遠い昔の修道院の響きを想像してみませんか?





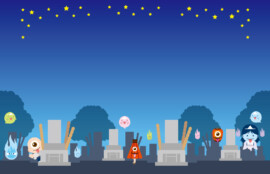









この記事へのコメントはありません。