“音が前に出ない” ― それは誰もが通る壁
どれだけ丁寧に演奏しても、録音した音を聴き返すと「なんだか奥に引っ込んで聞こえる」ことがあります。
それは機材や環境のせいだけではなく、音を“前に出す”感覚そのものを理解していないだけかもしれません。
1. 【アタックと減衰】を意識してみる
音の輪郭を決めるのは「出だし」—つまりアタック部分です。
同じフレーズでも、アタックが立っているかどうかで存在感は大きく変わります。
| 状況 | 聴感 | 改善の意識 |
|---|---|---|
| ピッキングが浅い | 柔らかいが埋もれやすい | 少し強めに“弦を押し出す”意識 |
| ブレスが弱い | 音が奥に引っ込む | 息の勢いを“前方に送る” |
| ドラムのアタックが小さい | 全体が曇る | スティックの戻りを早く |
小さな変化でも「空気の押し出し方」を意識すると、録音した音の距離感が変わります。
2. 【音の重心】を整える
音が“前に出ない”とき、多くの場合は低域の使い方に原因があります。
低音が広がりすぎると、音の焦点がぼやけてしまうのです。
◯ 前に出る音 → 重心:中域中心(250Hz〜2kHz)
△ 引っ込む音 → 重心:低域寄り(60Hz〜120Hz)
ベースやアコギの場合、低音を出すよりも「響きをコントロール」することが重要です。
スタジオでは、壁の反射や床の共鳴も含めた“空間の重心”を聴いてみましょう。
3. 【空間の抜け道】を作る
ミックスでも生演奏でも、音が前に出ない最大の理由は「スペースの奪い合い」です。
同じ帯域・同じ位置に音が重なっていると、どんなにいい演奏でも立体感が失われます。
| 例 | 解決策 |
|---|---|
| ボーカルとアコギがぶつかる | アコギのリズムを“裏”にずらす |
| ピアノとベースが重なる | ピアノを軽くオクターブ上に配置 |
| シンバルが被る | 打点を間引く・叩く角度を調整 |
これは“ミックス”以前に、アンサンブルの設計の話です。
演奏中に「他の音に空気を譲る意識」ができると、自然と音が前に出てきます。
🎧 練習でできること
EQやコンプレッサーを使わずとも、「音の前後感」を育てることは可能です。
おすすめは次のような練習法です。
- スタジオで録音 → スピーカー再生 → 自分の位置を変えて聴く
- 同じフレーズを“アタック強め”と“柔らかめ”で弾き比べる
- 他人の演奏を背後から聴き、「どの位置で鳴っているか」を言語化する
音の“立ち上がりと居場所”を掴めるようになると、
どんな環境でも「自分の音を前に出す」ことができるようになります。
🎵 最後に
音が前に出るかどうかは、テクニックよりも“耳の意識”が左右します。
iB MUSIC STUDIO & Schoolの各部屋は、音の反射や明るさが異なる設計になっており、
「音の立ち方」「空間の響き」を確認する練習に最適です。
ぜひ、自分の音の“前後感”を体験しながら磨いてみてください。







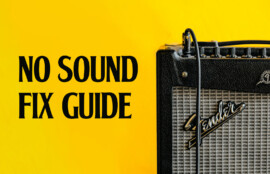







この記事へのコメントはありません。